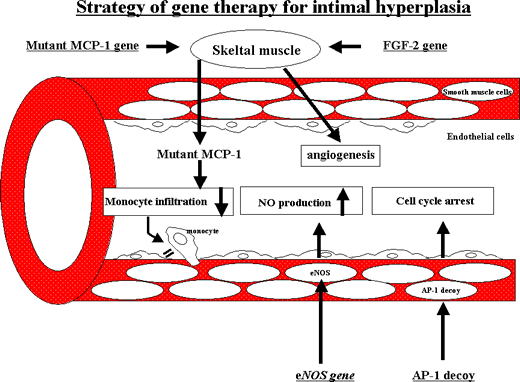| 消化管 | 肝胆膵 | 呼吸器 | 移植 | がん先端医療 | 外科集学的 治療学 |
| 乳腺 | 脾・門脈 | 血管 | がん分子 病態学 | 外科分子 治療学 |
消化器・総合外科(第二外科)の研究部門は、疾患別研究グループで構成されており、
基礎的研究から臨床的研究まで、積極的に研究活動を行なっています。
◆ 九州大学臨床研究倫理審査委員会の承認を受けた研究について
PDFファイルをご覧いただくにはAcrobat Reader(無償)が必要です。
お持ちでない方はこちらよりダウンロード下さい。
消化器・総合外科(第二外科)血管グループは、我が国における血管外科領域のパイオニアの一つであり、臨床・研究面ともに活発な活動を行っています。
臨床面においては、動脈瘤と閉塞性動脈硬化症が手術症例の大部分を占めるようになっている。近年の動脈硬化性疾患の増加に伴うものと考えられるが、更に、虚血性心疾患や脳血管障害などの併存疾患の合併頻度や重症度が増し、全身的にはハイリスク患者が増加している。また、動脈硬化性病変は広範囲・末梢側へ及ぶので、複数のバイパス術や、より末梢側へのバイパスが必要な症例も増えている。すなわち、より複雑な血行再建を要する症例ほど全身的にはハイリスクであり、大動脈・腸骨動脈領域の病変に対しては、非解剖学的バイパスや血管内治療の併用による手術の低侵襲化を図るようにしている。また、閉塞範囲が広範囲に渡るため、足関節レベルへの遠位バイパスが必要な症例も増加している。動脈硬化が進行した閉塞性動脈硬化症症例には血行再建不能な症例もあり、このような症例に対して治療的血管新生療法が注目されている。教室においても、末梢血幹細胞移植による血管新生療法を既に行い、良好な結果を得ている。間もなく、血管新生因子であるFGF2遺伝子を搭載した組み替え型センダイウイルスベクターを用いた血管新生療法の臨床試験を開始した。
研究面においては、血管内膜肥厚の機序解明とその制御が主要な研究テーマであったが、血管新生療法を含めた再生医療に関する研究や動脈瘤の病因解明のための遺伝子解析などにも研究分野を広げている。遺伝子治療の基礎的研究に加え、低出力体外衝撃波を用いた血管新生療法、血管内皮前駆細胞に関する研究、人工血管の開発など他教室との協同で研究を行っている。